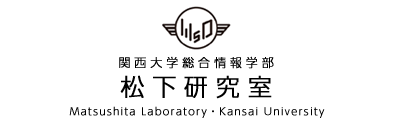十三期生 / 研究活動 / 藤川雄翔
Posted on 2025-07-30
第12回コミック工学研究会で発表しました(藤川)
皆さん,こんにちは!夏が始まったばかりなのに,暑すぎるせいですでに春と秋が恋しくなっている藤川です…
今回は2025年7月26日(土)〜27日(日)に,熊本県熊本市にある熊本大学で開催されました第12回コミック工学研究会で「物語間の共通性と差異性に着目したコンテンツナビゲーションに関する基礎検討」というタイトルで現地にて口頭発表をしてきましたのでその報告をさせていただきます.
今回の発表は,9月から大学院博士後期課程に進学予定である私のこれからどういった方向性で研究を進めていこうとしているのかを整理し,示すことを目的として発表をしてきました.
発表内容
タイトル: 物語間の共通性と差異性に着目したコンテンツナビゲーションに関する基礎検討著者: ⚪︎藤川 雄翔,松下 光範,山西 良典
解説:
みなさんは自分がこれから読んでみたいと思う物語に出会いたいとき,どのような方法で物語を探しますか?多くの人は,検索サイトやアプリなどで,タイトルや著者名,キーワードで検索をすると思います.もしくは,ジャンルやタグである程度物語を絞り込んでから探しに行くのではないでしょうか?しかし,物語を探したいときはこの方法でいいのでしょうか?確かに現状ではこの方法でも不満はないですが,かと言って私は十分だとも思っていません.私の研究は物語の探し方,出会い方をよりよくしていくための研究であると考えています!
私は新しい物語との出会い方には,大きく分けて受動的な出会い方と能動的な出会い方の2種類あると考えています.受動的な出会い方では,SNSなど身の回りの人が話題にしているから,ネットの広告などで目に入ったから,アプリでオススメとして上がってきたから,のように物語に出会うことを指します.それに対して,能動的な出会い方は,自分からジャンルやタグ,キーワードで検索して探すこと,自分より知っている人に聞いてみることで物語に出会うといったものです.現状のこれらの方法では自分が”好き”だと思える物語に出会える可能性はそこまで大きくないように思えます.出会える物語に出会う,楽しむために自分の好きなストーリーの物語を読んだり,見たりしたくないですか?そのためには,まだ知らない物語を自分から探しに行く,能動的な出会い方を充実させる必要があります.
私の研究は物語の出会い方をより良いものにするために,「自分の好みに合う物語を,類似する物語の中から探し出せる新たなナビゲーション手法の実現」を目的としています.自分の好きなストーリーから物語を探したいなら,「主人公が知らない価値観に触れて理解を深めていく物語」や「優しい男の子が気になる女の子の言動で心が乱される物語」のようにストーリーの内容を文章から探したくないですか?そのため,私の研究では,このような物語の主題を端的に表す文章に着目し,その文章をコンセプト文と呼んでいます.
コンセプト文はキャラクタや舞台設定を変化させても変わることのないストーリーの根幹を表した文章です.つまり,コンセプト文は複数の物語に当てはまる文章となります.例えば,「DRAGON BALL」(©️鳥山 明,集英社)や「ONE PIECE」(©️尾田 栄一郎,集英社),「鬼滅の刃」(©️吾峠 呼世晴,集英社)は,それぞれ設定は異なりますが,「平和を脅かす敵を倒す物語」というように説明することができます.コンセプト文は物語同士の共通点を説明することができるのです.また,コンセプト文は1つの物語に1つだけとは限りません.複数のコンセプト文で1つの物語を説明することもできます.例えば,「名探偵コナン」(©️青山 剛昌,小学館)は「主人公が難事件を次々に解決する物語」や「幼馴染との恋愛模様を描いた物語」,「さまざまなアイテムを駆使して,解決に導く物語」といったような複数のコンセプトで物語を説明できるはずです.このようになるのは,物語は受け手が変わることにより物語の解釈も変わるからです.
コンセプト文だけが物語のストーリーの内容を表す文章ではありません.これまでのストーリーの流れを示すあらすじ文,レビュワーの物語の印象を表すレビュー文,ストーリーを一文で説明する一言説明文があります.ここでコンセプト文と似ている一言説明文に少し触れます.一言説明文はいわば,昨今のライトノベルのような長いタイトルによりストーリーの内容を説明した文章のようなものであり,特定の物語のみについて説明した文章になります.そのため,複数の物語を説明できるコンセプト文とは少し異なります.これらのストーリーの内容を表す文章であるあらすじ文,レビュー文,一言説明文はコンセプト文とは違い,物語同士の共通点に言及することは少ないです.
では,コンセプト文はどのような場面で活用することができそうでしょうか?私は(1)検索,(2)推薦,(3)内容把握,の3つの場面で活用できると考えています.
まず検索では,コンセプト文をそのまま検索文として利用する方法があります.しかし,物語をコンセプト文のように短く言語化することは多くの人にとってはハードルが高いものとなってしまいます.そのため,コンセプト文をあらかじめ物語に付与しておき,好きな物語を説明する複数のコンセプト文の中から自分が興味のあるコンセプト文を選択し,物語を探す方法も考えられます.
つづいて推薦では,コンセプト文を推薦理由としての根拠として利用できると考えています.従来の物語の推薦では,自分と似た他のユーザが読んでいる物語をシステムが推薦してきます.どの物語を読んだことで推薦された物語が決定したのか,読んだ物語と推薦された物語はどういった観点で類似しているから推薦されたのかは,わからないのがほとんどです.そのような推薦方法では,「推薦された物語を読んでみよう!」となることは多くないと思います.そこで,コンセプト文の出番です!コンセプト文は物語同士の共通点を説明してくれます.物語同士の共通点が示されることで,「自分の好きな物語と〇〇という観点で類似しているから推薦している」ということが明確になり,推薦された物語に対する興味が湧いてくると思います.
最後に内容把握では,一つの物語に付与された複数のコンセプト文を読むことで,その物語がどういう物語なのかよりわかるようになるかと思います.物語を楽しむ前にコンセプト文を読むと,どんな物語なのかある程度把握してから見ることができます.物語を楽しんだ後では,物語に対する理解が深まるかもしれません.もしかすると,物語の意外な一面も発見できるかもしれません.また,コンセプト文は複数の物語を説明することができるため,自分が読んできた物語から,自分がどういった物語が好きなのか文章として説明され,自分の好きな物語を把握することができると思います.さらに,類似している物語同士で,コンセプト文に書かれていない要素もコンセプト文と一緒に見せることで,読んでいない物語に対して興味が湧いたり,類似している中でもどういう違いがあるのかを把握することもできるようになります.
コンセプト文って面白そうじゃないですか?私はこれからの博士後期課程の間で,このコンセプト文の実用化に向けて精進していこうと思っています.
ここまで読んでいただきありがとうございました!より詳しい内容を知りたい方は,ぜひ下記にある発表スライドや論文まで読んでみてください!!!
発表スライド:
論文情報
藤川 雄翔, 松下 光範, 山西 良典. 物語間の共通性と差異性に着目したコンテンツナビゲーションに関する基礎検討, 電子情報通信学会第12回コミック工学研究会, pp.35-38, 2025.感想
これで,コミック工学研究会での発表は3度目になります.学会での研究発表はもうだいぶ慣れてきました.漫画が本当に大好きだ,面白いと思っている研究者の方や出版社の方が大勢いて,発表のたびにいただくコメントが参考になるものや,興味深いものばかりで毎回楽しいと思えるのがコミック工学研究会です!もちろん,他の研究発表も着眼点が面白いもので溢れていて,毎回わくわくしながら聴いています.これからもコミック工学研究会には論文を出していき,お世話になりたいと思います!!(笑)これから,博士課程に進学し,ますます忙しくなっていくと思いますが,しっかりと研究成果を着実に積み上げていきたいです!!!💪🔥
最後になりますが,論文や発表スライド等に関してご指導いただいた松下先生,山西先生に感謝申し上げます.ありがとうございました.

(文責:藤川)
Related Posts